化学が苦手なあなたへ
本記事では知っていると得をする中学理科化学単元の語呂合わせ&テクニックを紹介いたします。
実際に現役学生から「解説してほしい!」という声が多かった単元をピックアップしてみました。
原子量
水素・炭素・窒素・酸素の4つの原子の重さの比は、覚えておくととても便利です!
高校化学で「原子量」として学習するのですが、中学生のうちから覚えておくと、問題を解く際に利用できることがあるのです。
H(水素原子)=1 とすると
C(炭素原子)=12
N(窒素原子)=14
O(酸素原子)=16
この割合をぜひ覚えておいてください。
中学校の先生はこれらの数値をもとにして問題をつくっているので、ふつうこの数値を教えてくれません。
逆の発想をすると、これらを覚えていれば、問題の根幹が一気に分かる可能性があるということになるのです。
「水平リーベ、僕の船…」で「H、He、Li、Be、B、C、N、O、F、Ne…」という原子番号順を覚えている方はラッキー!
今回出てきた1、12、14、16という各原子の原子量も、次のように合わせて覚えてしまうことができるのです。
Hは原子番号「1」番なので、そのまま原子量「1」です。
Cは原子番号「6」番なので、原子量は2倍して「12」と計算して求められます。
Nは原子番号「7」番なので、原子量は2倍して「14」と計算して求められます。
Oは原子番号「8」番なので、原子量は2倍して「16」と計算して求められます。
では、これらを利用できるパターンを3つ紹介いたしましょう(化学反応式は書ける前提でご覧ください)。
黒鉛(炭素)の完全燃焼
化学反応式は次のようになります。
C + O2 → CO2
この時点で筆者は「黒鉛(炭素)3gに酸素8gが結びついて二酸化炭素11gができる」と答えられます。
原子量がCが12、Oが16なので…
・Cは原子量12なので「重さ12g」としましょう。
・するとOが原子量16なので、O2は16×2で「重さ32g」となります。
質量保存の法則により、CO2は12+32で「重さ44g」となります。
以上から重さの比は、黒鉛(炭素):酸素:二酸化炭素=3:8:11と求められますね。
実際は問題文に「黒鉛24gを完全燃焼させると気体が88g生じた。」という感じで表記されています。
原子量を知っていると、この情報の意味がよく分かりますね。
アンモニア
時々出てくるアンモニア。化学式はNH3ですね。
この時点で筆者は「アンモニアの中の窒素の重さ:水素の重さ=14:3」といえます。
原子量がHが1、Nが14なので…
・Nは原子量14なので、「重さ14g」としましょう。
・するとHは原子量1なので、H3は1×3で「重さ3g」となります。
つまり原子量を覚えていれば、化学式をみるだけで含まれている原子や分子の重さの比を暗算できてしまうのです!
エタノール(C2H6O)の燃焼
アルコールの一種であるエタノールを燃焼させる化学反応式は次のようになります。
C2H6O + 3O2 → 2CO2 + 3H2O
原子量がHが1、Cが12、Oが16なので…
・C2H6O(エタノール)の重さを12×2+1×6+16=46gとします。
・3O2(酸素)の重さは3×16×2=96gとなります。
・2CO2(二酸化炭素)の重さは2(12+16×2)=88gとなります。
・3H2O(水)の重さは3(1×2+16)=54gとなります。
以上から反応の際の重さの比は、エタノール:酸素:二酸化炭素:水=46:96:88:54=23:48:44:27と求められます。
これらの知識さえあれば、次のような問題が出てもすぐに解けます。
(1) ある重さのエタノールを完全燃焼させたとき、水が108g生じた。エタノールに結びついた酸素の重さは何gか。
求め方と答え → 48g×108g/27g=192g
(2) エタノールの中に含まれる炭素、水素、酸素の重さの比を最も簡単な整数比で求めよ。
求め方と答え → 12×2:1×6:16=24:6:16=12:3:8
実際には(1)や(2)のような問題は、文中に複雑な条件が書かれており、そこから思考と計算を重ねて答えを出すのが一般的。
問題制作者が利用している原子量の数値を覚えておくと、その面倒な過程をスッ飛ばして一気に答えに辿り着けるのです。
何だか罪悪感さえ出てきますが、数値のルールが決まっているので利用しない手はありません。
(もちろん、その後実際に解いてみて正しいかどうか確認してみてくださいね!)
練習問題
原子量を上手く使いこなせるかどうか、次の練習問題で確認してみてください。
※水素、炭素、酸素の各原子1個あたりの重さの比は1:12:16とします。
(1) 黒鉛(炭素)を不完全燃焼させると、一酸化炭素(化学式CO)が発生する。
このときの黒鉛、結びついた酸素、できた一酸化炭素の重さの比を最も簡単な整数比で求めよ。
(2) メタノール(化学式CH4O)に含まれる炭素、水素、酸素の重さの比を最も簡単な整数比で求めよ。
(3) プロパン(化学式C3H8)を完全燃焼させると、二酸化炭素と水が生じる。
このときのプロパン、結びついた酸素、二酸化炭素、水の重さの比を最も簡単な整数比で求めよ。
↓解答と解説は下にあります↓
↓
↓
↓
(1)の求め方
化学反応式は「2C + O2 → 2CO」
・炭素の重さを2×12=24gとする。
・酸素の重さは16×2=32gとなり、質量保存の法則から一酸化炭素の重さは24+32=56gとなる。
よって、24:32:56=3:4:7と求められる。
(2)の求め方
・炭素の重さを12gとする。
・水素の重さは1×4=4gとなり、酸素の重さは16gとなる。
よって、12:4:16=3:1:4となる。
(3)の求め方
化学反応式は「C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O」
・プロパンの重さを12×3+1×8=44gとする。
・酸素の重さは5×16×2=160g、二酸化炭素の重さは3(12+16×2)=132g、水の重さは4(1×2+16)=72gとなる。
よって、44:160:132:72=11:40:33:18となる。
全問正解できましたか?
これらの比さえ求めてしまえば、あとは比例計算を繰り返していくだけでいろんな問題に対応ができるようになっています。
中2化学:銅と酸化・マグネシウムの燃焼
銅、マグネシウムなどの金属を酸化・燃焼させる問題では、必ずといっていいほど計算が出てきます。
文中や表、グラフの数値や関係を読み解き、質量の関係を導き出していくのが一般的なのですが…面倒!
実際には、金属の重さと結びつく酸素の重さ、そしてできる酸化物の重さの比が各金属によって決まっています。
であれば…語呂合わせであらかじめ覚えてしまいましょう。
銅の酸化
銅4gを完全に酸化させると、酸素1gが結びつき、酸化銅(黒色)が4+1=5gできます。この語呂合わせはコチラ!
良い子(4:1:5)は参加するドー(酸化銅)!
まさに一撃必殺。事前にこの比を覚えていれば、問題がとても見やすくなることでしょう。
早速問題を引っ張り出してきて、「良い子」の関係を探してみてください。
ただし、実験誤差によって多少の数値のずれがある可能性もあります。
マグネシウムの酸化
マグネシウム3gを完全に酸化させると、酸素2gが結びつき、酸化マグネシウム(白色)が3+2=5gできます。この語呂合わせはコチラ!
3つ子が参加(酸化)?マジ(Mg)?
こちらの反応は酸化銅ができるときとは異なり、激しい発光を伴う燃焼反応であるということに注意してくださいね。
マグネシウムの燃焼実験も、銅の酸化実験のときと同じように、実験誤差によって多少の数値のずれがある可能性もあります。
試験ではこれが出る?「差がつく」問題シリーズ
ただ理解しただけでなく、テストや入試で結果を出さなければ意味がありません。
そこで、銅の酸化、マグネシウムの燃焼という単元で「差がつく」問題を厳選してみました。一度解いてみてください。
(1) 25gの銅の粉末を加熱すると、一部が酸素と結びつき27gの粉末に変化した。酸素と結びつかなかった銅は何gか。
(2) 同じ重さの銅、マグネシウムに結びつく酸素の最大の重さの比を、最も簡単な整数比で求めよ。
(3) 同じ重さの酸素に結びつく銅、マグネシウムの重さの比を、最も簡単な整数比で求めよ。
(4) 銅とマグネシウムがまざった粉末が10gある。この粉末を完全に酸化させると15gの粉末に変化した。
この粉末に含まれている銅の重さは何gか求めよ。
↓解答と解説は下にあります↓
↓
↓
↓
(1)の求め方
27g-25g=2gの酸素が結びついたことがわかります。
酸素と結びついた銅の重さをxgとすると、x:2=4:1となり、xg=8gとなります。
以上から、25g-8g=17gと求められます。
(2)の求め方
重さの比は銅:酸素=4:1、マグネシウム:酸素=3:2なので、銅とマグネシウムの重さを3と4の最小公倍数の12でそろえます。
重さの比は銅:酸素=12:3、マグネシウム:酸素=12:8となり、求める比は3:8となります。
(3)の求め方
重さの比は銅:酸素=4:1、マグネシウム:酸素=3:2なので、酸素の重さを1と2の最小公倍数の2でそろえます。
重さの比は銅:酸素=8:2、マグネシウム:酸素=3:2となり、求める比は8:3となります。
(4)の求め方
重さの比は銅:酸化銅=4:5なので、銅の重さを4xとおくと、酸化銅の重さは5xとなります。
重さの比はマグネシウム:酸化マグネシウム=3:5なので、マグネシウムの重さを3yとおくと、酸化マグネシウムの重さは5yとなります。
4x+3y=10 5x+5y=15 これを解いてx=1となり、求める銅の重さ4xは4×1=4gとなります。
中3化学:水の電気分解
H字管に入れた水に電気を流す実験で、定期テストや高校入試にほとんどそのまま出題されます。

陽極側には酸素が、陰極側には水素がそれぞれ発生し、その発生した体積比は1:2になります。
…という事柄を一気に覚えてしまう語呂合わせを紹介いたしましょう。それがこちら!
1、2、3、4、用意ドン!
(1、2、酸、水(すぃー)、陽、陰)
体積比1:2の割合で、酸素と水素が、それぞれ陽極と陰極に発生することをまとめた語呂合わせです。
なお、酸素と水素が体積比1:2で発生することは化学反応式にも記されています。
2H2O → 2H2 + O2
2H2O → O2 + 2H2 (上の式と比べて、水素と酸素の順を左右反対に並び替えました。)
2H2O → 1O2 +2H2 (上の式と比べて、酸素の化学式の前に係数「1」を追加しました。)
赤字部分に注目すると、確かに酸素:水素=1:2という体積比の数値が式の中にそのまま表記されていますね。
教科書などには「同温・同圧下において、気体の体積は分子数に比例する」と書かれている内容です。
こちらの反応も、上で紹介した原子量を覚えていれば重さの比を求めることができますね。
原子量がHが1、Oが16なので…
・2H2Oの重さを2(1×2+16)=36gとしましょう。
・すると、2H2の重さは2(1×2)=4gと求められます。
・さらに、O2の重さは16×2=32gと求められます。
この反応の際の重さの比は、水:水素:酸素=36:4:32=9:1:8という関係になるわけですね。
【関連】中2化学:水素の燃焼
水の電気分解の逆の反応も問題として水素の燃焼が出題されることがあります。
この際ですからまとめて覚えてしまいましょう。
火のついたマッチを水素に近づけると「ピョン」と音を立てて爆発して水ができる反応です。
2H2 + O2 → 2H2O
こちらも同様に、反応の際の重さの比は、水素:酸素:水=1:8:9となります。
一躍(いちやく)水素爆発!
と覚えてしまってもよいでしょう。
問題制作者と同じ視点で問題を見よ
今回はかなりアウトローな切り口から化学単元を解説いたしました。
生徒視点ではなく教師視点で物事をみると、問題制作の意図が理解できて解きやすくなるのです。
そのための第一歩として、物質の重さのルール「原子量」を覚えてみましょう。
化学の苦手意識が少しでも減ることを祈っております!
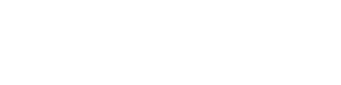



コメントを残す