皆さんは普段、どんな環境で勉強をしていますか?
静かな自宅の自分の部屋や図書館、それよりかはちょっとガヤガヤしているリビングやカフェ。
皆さんの普段勉強している環境は方によって様々だと思います。しかし、1度はこんな経験ないでしょうか?
「音楽を聞きながら勉強したい…!」
もはや音楽を聞いていないと勉強なんてできない!なんて方もいるかも知れません。
ただ、なんとなく勉強の妨げになるような気がするのも事実。
今回はそんな勉強中の音楽への疑問を一気に解決します!
目次
そもそも音楽が脳に与える影響とは?
まずは勉強中に限らず音楽が脳にどのような影響を及ぼしているのかを見ていきましょう。
音楽を聴いているとテンションが上がり、心地よい気分になりますよね?
これは脳の神経伝達物質であるドーパミンが前頭葉に放出されることによるものです。
ドーパミンというのは快楽や意欲を司るホルモンの一種です。
ドーパミンが放出されるとモチベーションが上がり、疲労感が減少するといわれています。
そしてこのドーパミンという物質は、好きな音楽を聴いているときに多く放出されます。
よって単純に音楽を聴いてやる気を出し、意欲的に活動したいときには好きな音楽を聴くことが効率のよい方法だということですね!
出典:https://www.afpbb.com/articles/-/2782051
勉強中の音楽は大丈夫なのか
音楽が脳にいい影響を及ぼすことはわかりました。
次は勉強中に音楽を聴くことによる影響をみていきます。
脳には右脳と左脳が存在するというのはご存知だと思います。
それでは右脳と左脳、それぞれどんな働きをしているかはご存知でしょうか。
右脳はイメージ脳ともいわれ、
視覚情報や音楽、立体的なイメージなど直感的な思考を管理しています。
対して左脳は
言語や計算など論理的な思考を管理しているのです。
このことを考えると、
「音楽を聴くのは右脳、勉強は左脳っぽいから使う脳の部位が違うので影響はないのでは」
なんて想像ができます。
しかし、歌詞の入った曲で歌詞の意味を理解しているときはどうでしょう?
歌詞は言語なので、左脳で考えている状態なのです。
このような状態で勉強をすると、左脳が勉強だけに集中できず、
やはり効率が下がってしまうのです。
以上のことから、理論的には勉強中の音楽は歌詞の入っているものは避けたほうがいいということになります。
ただ、こんな経験を聞くこともあります。
「音楽を聴いて勉強していたら集中していてほとんど耳に入ってなかった」
この状態はいうなれば「ものすごく集中している無敵の状態」、スポーツで言うとゾーンみたいなものですね。
ある種の特殊な状態です。
この状態に入ったのであれば、音楽はもう意識していないので音楽の種類は関係ありません。
こうした状態が作れるようであれば、無敵状態が終わるまで思いっきり勉強しましょう!
出典:http://www.seibutsushi.net/blog/2013/12/1451.html
音楽をうまく活用する方法
今までのことを踏まえて音楽をうまく活用していく方法を考えてみましょう。ここでの目標は先ほど最後に説明した音楽を意識していない状態、無敵状態を作り出すことです!
まずは勉強を始める前です。人間の脳はものごとを始めてからやる気がでるようになっているので始める前というのはなかなかやる気が出ません。
なのでなかなか勉強を始められないという方は勉強を始める前に好きな音楽を聴いてモチベーションを向上させましょう。
勉強を始める前はこの曲!という風に決めておいてルーチンワークにするのもおススメです!勉強を始めた後、すぐに無敵状態に入れるという方は勉強開始後に音楽なしで勉強していってもいいかもしれません。
問題は勉強を始めた後、なかなか集中できないパターンです。勉強に集中できないと音楽に意識をもっていかれることも多いので好きな音楽を聴き続けて勉強するというのはおススメできません。なので音楽を聴くのをやめるか歌詞のない音楽や自然の音に切り替えるようにしてみましょう!
筆者はこのようなとき、YouTubeで波の音や森の音などの音源を聴きながら作業をしています。科学的にも全くの無音より適度な環境音があったほうが脳の働きが良くなるという結果がでています。
自分の状態に合わせて音楽を聴くタイミングや種類を変えるのが賢い音楽の使い方といえるでしょう。
音楽を聴きながら勉強をするときの注意点は?
音楽を聴きながら勉強するにも気を付けなければいけないことが2つほどあります。
1つめは試験の本番では音楽は流れていないということです。
勉強をしている方は試験に合格するために勉強をしている方が多いと思います。
もちろん試験会場で音楽を聴きながら受験するということはできません。
そのため、音楽がないと集中できない!といった状況になるのは避けましょう。
音楽のようにドーパミンを出すことには依存性があります。
音楽に依存しないためにも
「普段から過去問を解くときは音楽は聴かない」
「試験の週は音楽を聴きながら勉強をするのをやめる」
など試験の環境でも100パーセントの実力が発揮できるような調整をしましょう!
2つめは音楽と相性の悪い科目も存在するということです。
ズバリ国語と英語は相性がよくありません。
2つの科目とも言語を扱います。
脳は同時に2つの言葉の情報を処理することはできません。
そうなるとちょっとでも音楽に気を取られてしまうと勉強がストップしてしまいます。
歌詞のある音楽は極力避けるようにして効果的に勉強が進むようにしましょう。
暗記系の科目は耳から記憶したほうが脳に定着します。
そのため自分で声に出して読み、単語のCDを聴きながら覚えるのが良いとされています。
そのため暗記をまとめてやってしまいたいときも音楽は聞かずに勉強をすることがおすすめです。
逆に数学や物理といった科目は言葉で情報を処理するといった機会は少ないので音楽との相性は良いです。
ただ、文系科目でも音楽を聴きながら勉強したほうが捗る方や逆に理系科目でも集中できない方もいます。
個人差があるので自分はどうなのか検討してから実践してみてください!
メリットとデメリット
最後にこれまでのことを踏まえてメリットとデメリットを挙げたいとおもいます。
・集中している状態がじぶんでもわかりやすい
・周囲の騒音に気をとられない
・音楽に気をとられることもある
・言語を扱う科目との相性が悪い
・音楽に依存してしまうパターンもある
このように音楽を聴きながら勉強することが一概にいい、悪いで説明できないことがわかります。自分が音楽を聴くことでどんな効果を期待しているのか、何を求めているのかを考えてみるのもよいでしょう!
自分に合った勉強法を!
これまで音楽と勉強の関係をみてきました。
音楽とは付き合い方が大事で音楽がないと勉強できないといった依存状態になるのはよくありません。あくまでも音楽は勉強のやる気を引き出すサポート役としてうまく使ってあげるのが勉強を効率よくすすめるポイントです。
ただ、効率的な方法というのは非効率なことや無駄なことを経験しないとわからないともいわれます。
上に挙げたようなメリットやデメリットを把握して自分にあった勉強法を編み出していってください!
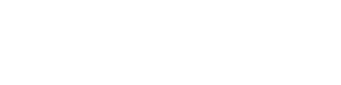



コメントを残す