現役高校生や大学生の方をはじめ、社会人になりたての方の中には「勉強は学生がするもの」と思っている方は多いのではないでしょうか。実は、社会人になっても勉強をする機会はたくさんあります。
例えば、仕事の昇給に必要な試験を受けたくなった場合、資格が必要な仕事をすることになった場合など働きながら勉強をしなければいけなくなる機会は多いです。
もちろん、会社で必要だからという理由以外で勉強をしている社会人もたくさんいます。
例えば、もっと色々なことを学びたいとか、他の同僚や先輩と差をつけるために常に知識を身に着けていたい、ずっと夢だった難易度の高い英検や漢検を受けるために勉強がしたいという社会人もたくさんいます。
しかし、社会人が勉強をすることになると、「時間がない」「働きながら勉強をすることが難しい」「やる気がなかなか出ない」といった壁にぶつかって悩んでしまう方がとても多いです。
今回の記事では社会人がやる気を出しつつ、勉強をしていく方法をご紹介します。
目次
社会人が勉強をするためにはやる気を引き出すことが大切
社会人として会社で働いている方はとてもよくお分かりだと思いますが、仕事をして疲れて帰ってきたあとに勉強をすることは至難の業です。
ついつい寝てしまったり、疲れすぎて勉強をする元気なんて出ない……という経験をして挫折してしまった……という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのため、社会人が勉強をするためには「やる気」を常に引き出しておく必要があります。自分がやる気モードにある時間を増やさなければ、至難の業である「仕事をしつつ勉強を進める」ということはできません。
そもそも「やる気」とはなにか
一般的に私たちが「やる気」と呼んでいるものは、甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン(通称やる気ホルモン)のことです。
長ったらしい名前ですし、英語でも”Thyrotropin-Releasing Hormone”と長いので、その頭文字を取ってTRHと略されます。
このやる気ホルモンは、脳の中にある「視床下部」と呼ばれる体温調節や睡眠などの私たちの生命維持に関わること全般をまとめて支配している部分で分泌されています。
このやる気ホルモンは脳を活性化させてくれるため、TRHが分泌している間は空腹感を忘れて没頭したり、何時間も集中して物事を進めることができます。私達のやる気は、このやる気ホルモンが分泌されることによって生まれるものです。
やる気をだすためには「やる」ことが大切
やる気が出ない……と思いつつ数時間経ってしまったという経験はありませんか?
実は、何故やる気が出ないかというと「やっていない」からなんです。
社会人には、勉強できる時間が非常に限られています。そのため、少ない時間で勉強を進めるために先程説明したやる気ホルモンを素早く分泌させる必要があります。
そのためには、行動を起こすことが必要不可欠です。
やる気というと、なにかをする前に湧き出てくるというイメージがとても強いですが、実はやる気は行動を起こすことによって初めて生まれるものだということをご存知でしょうか。
例えばあなたが今、試しに「やったー!」とガッツポーズをしたとします。そうすると、なんとなく達成感が湧いてくるのではないでしょうか。
これは、ガッツポーズをするという「行動」をしたことによって「達成感」という「感情」が生まれるという仕組みなのです。
私たちの「嬉しい」「悲しい」といった感情や「やる気」などの気分の元となるのは脳ではなく身体です。
脳にスイッチを入れるのは身体であるため「勉強をはじめる」という行動を起こさなければ、気分である「やる気」は湧いてこないという仕組みになっています。
それでは、素早く勉強のやる気を出すにはどうしたら良いのでしょうか。
「5分だけ」勉強をする
勉強というと、何時間も取り組むものと思ってしまうという方も多いのではないでしょうか。
あれもしなければ、これも覚えなければ……とやることの多さに呆然としてしまってやる気が出ないという経験をしたことがある方もいらっしゃると思います。
そうなってしまっては、やる気は当然出ません。
そのため「5分だけここを覚えよう、このページを読もう」などと決めて取り組むようにしてみてください。
5分というとても短い時間であれば、気持ちも沈みにくくなりますし勉強にも取り掛かりやすくなります。ですが、実際に勉強をはじめると5分だけでは物足りなくなり、結果として数十分、数時間進めてしまうことがほとんどです。
とにかく勉強をするという「行動」を起こすことによってやる気を引き出すことがとても大切です。
隙間時間を活用する
先程5分だけ勉強する方法をご紹介しました。これができるようになると、通勤中や休憩中などの「隙間時間」をうまく活用することができます。
10~15分程度の時間や30分~1時間程度の時間を使ったとしても勉強は進まない…と考えている方も多いかと思います。
ですが、例えば
- 通勤時間:2時間
- ご飯を食べ終えたあとの時間:40分
- 仕事後に電車を待っている時間:10分
これだけでも、合わせると約3時間になります。つまり、こういった隙間時間をうまく活用していけば、家に帰ったあとに勉強する時間もある程度少なくすることができます。
社会人には勉強に充てられる時間がとても限られているため、こういった隙間時間を使って少しづつ進めていかなければ、疲れてしまいます。
また、隙間時間に勉強をすることによって、勉強モードを保ちやすくなり「このあと勉強をしなければ」という気持ちも生まれやすくなります。勉強モードを保つためにも、帰宅後の負担を軽くするためにも、隙間時間の有効活用は必須です。
こちらの記事もご参照下さい。
「勉強をする」「勉強がしたい」という雰囲気づくりをする
勉強をするためには「雰囲気作り」もとても大切だということはご存知でしょうか。
自分を勉強モードにすることによって、誘惑に打ち勝てるようになったり集中して勉強を進めていくことができます。そうするためにも、まずは勉強するための「雰囲気作り」をするようにしましょう。
例えば、あなたは仕事から帰ってきた後や、お休みの日にリラックスをするときどのようにリラックスしていますか?
お気に入りのアーティストの音楽を聞いたり、映画や動画配信サイトで好きな動画を見たり、ソファーに寝転がったりするなどリラックスするためにはある程度決まったやり方で自分自身を休めているという方が多いのではないでしょうか。
しかし、そういった環境は勉強には不向きです。
普段リラックスしている環境で勉強をしようとすると、脳や体は「この雰囲気はリラックスをする雰囲気だな」と認識してしまい、集中して勉強をしなければならないときにもリラックスしてしまいます。
そのため、勉強をするときは
- 普段とは別の椅子や机を使うなど環境を大きく変える
- リラックスするときに聞いている音楽とは別の音楽を聞く
など、勉強モードに切り替えやすい環境作りをすることがとても大切です。
例えば「勉強をするときにはこのアーティストの曲を流そう」などと決めて勉強するための流れを作るようにすると、勉強を進めやすいです。
まとめ
いかがでしょうか。最後に、今回の記事で紹介した重要なポイントをまとめます。
- 社会人には、勉強をする時間が限られているため「やる気」を常に引き出すことが重要
- やる気の正体は「TRH(甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン)」というもので、行動を起こすことによって初めて分泌される。そのため、やる気を出すには実際に「やる」必要がある
- 隙間時間を活用したり、勉強に取り掛かりやすくするためにも「5分だけ」勉強をするつもりで暗記をしたり、テキストを読むとその後も捗りやすい
- 勉強モードを保つためにも、通勤時間や昼食後などはテキストを斜め読みしたりとにかく5分だけでも勉強をするようにする
- 勉強するための雰囲気作りをするため、普段とは違う場所で勉強したり聞く音楽を変える
しつこいようですが、社会人に勉強ができる時間は限られています。限られた時間をうまく有効活用ができなくて悩んでいる社会人の方は、今回紹介した勉強方法をぜひ試してみてはいかがでしょうか。
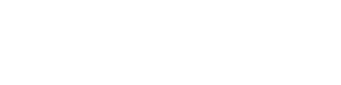



コメントを残す